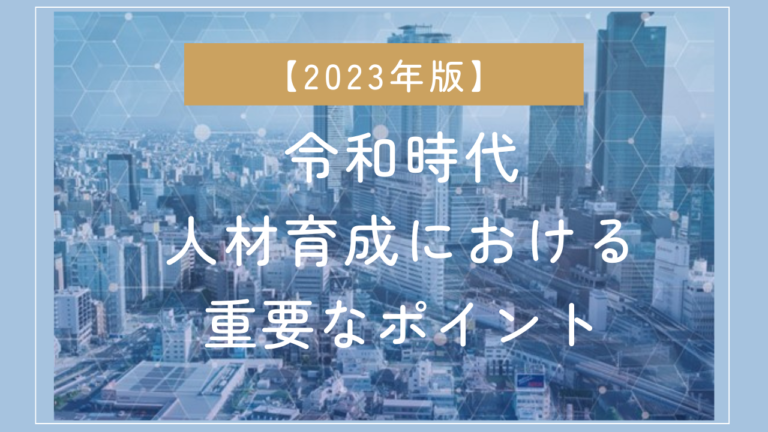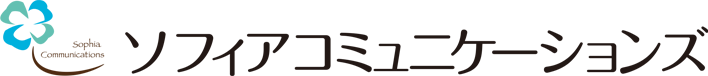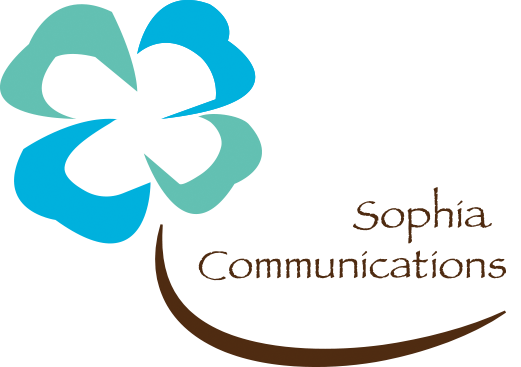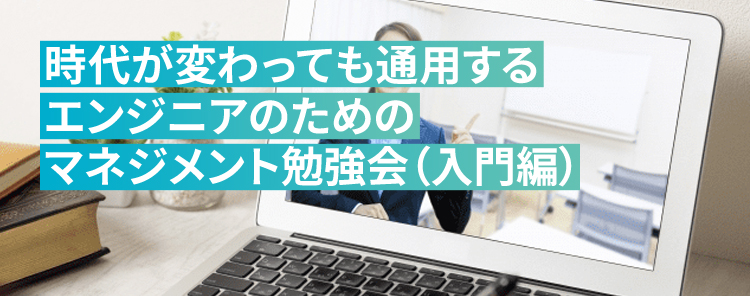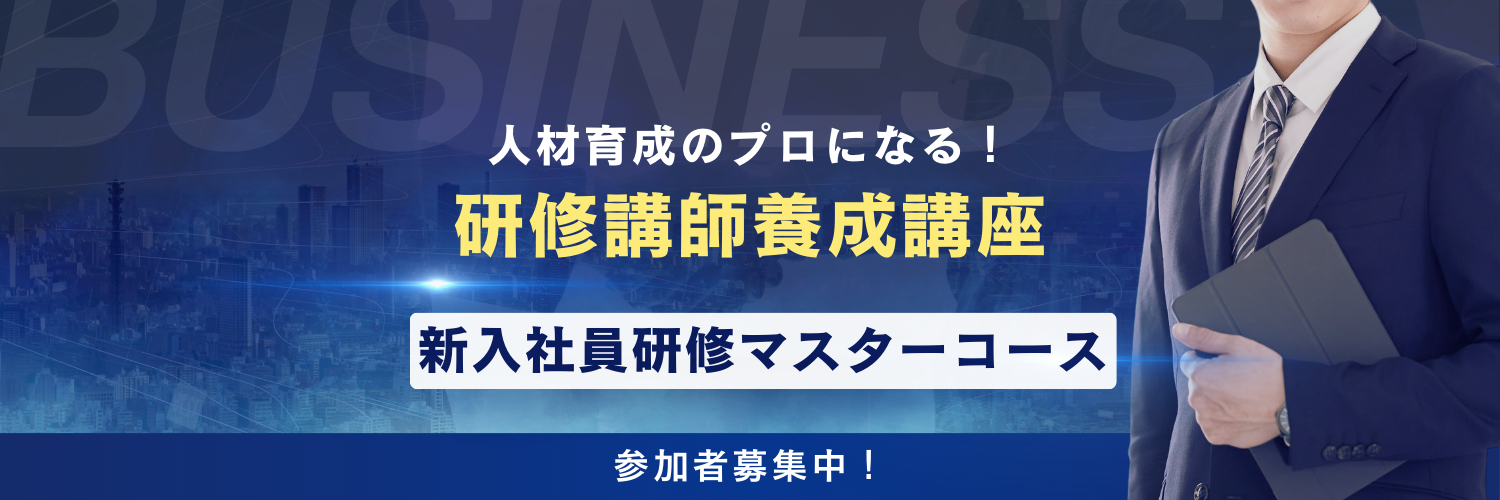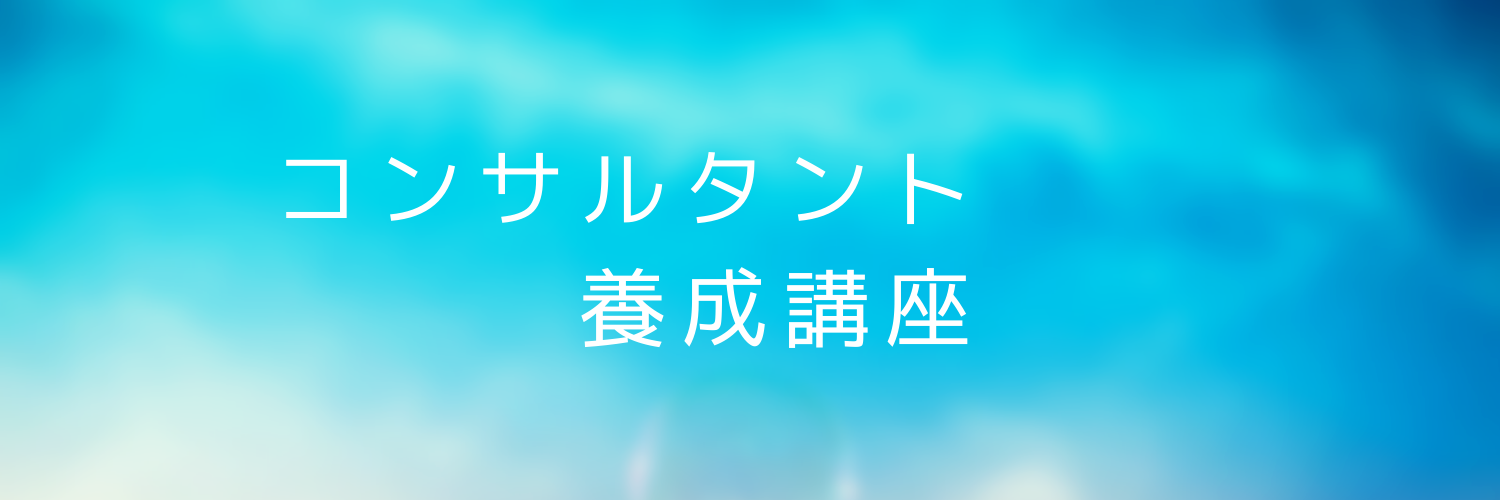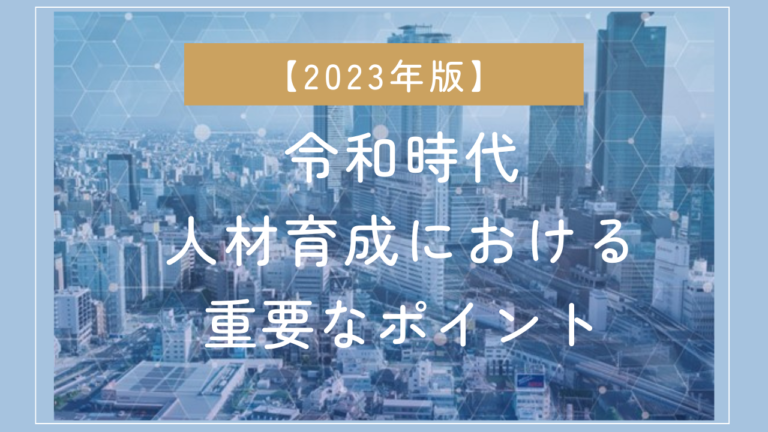

令和時代に入ると、人口が増加していた頃とは異なり、少子高齢化により労働人口は減少しています。企業の成長に貢献できる人材育成の重要性はますます高まっています。
時間とお金を投資する際に人材育成を重要な課題と考える企業がほとんどです。
社内の人材のスキルを向上させ、働きがいのあるものにすることが企業の成長にとって不可欠です。
今回は、企業が人材育成を進めるために何をどう考えるべきか(戦略)、具体的にどのような手法があるか(戦術)など具体的にポイントにまとめ紹介します。
令和時代の人材育成のポイントは昭和時代とは大きく異なる
昭和時代と平成時代の溝は深い

いわゆる「昭和世代」と「平成世代」とでは、価値観や考え方が大きく異なっています。そのため上司や管理職である昭和世代の人が、平成生まれの若者と昔の感覚で接すると、お互いに大きなギャップを感じるでしょう。
平成生まれの若者は、決して能力が低いわけではありません。ただ、昭和世代と平成世代の「当たり前」や「常識」に、著しい違いが生まれているのです。
そもそも人材育成とは
「人材育成」とは、社員を企業の成長・発展に貢献できる人材として育成することを意味します。社員のパフォーマンスを開花させることは、企業の成長に必要不可欠です。
「人材育成」といっても、新入社員や中堅社員、管理職など、育成対象に応じていくつかの種類があります。
それぞれで人材育成の目標が異なってくるのは言うまでもありません。例えば、新入社員向けであれば、社会人の基礎を理解・習得することに重きをおくことが大切です。
中堅社員となると何らかの専門性を身に付け、他のメンバーをディレクションできるようになることが目標となります。
出典:
「人材育成」の目標や考え方とは? マネジメント層を育てるうえでの大切なことや課題を解説
平成時代の新入社員は上下間のコミュニケーションが苦手

企業で人事・教育を担当する方の多くが、いまどきの新入社員とのコミュニケーションや接し方で悩んでいます。
彼らの特徴で真っ先に言われるのが、「何かを問いかけても反応が薄い!」ということです。
彼らは「デジタルネイティブ世代」といわれるように、物心ついたころからインターネットが身近にある環境で育っています。
ネットでの検索やSNSなどのバーチャルなコミュニケーションが圧倒的に増えた分、人と向かい合って会話する機会が減りました。これが「反応が薄い」原因の一つとしてあげられるかもしれません。
また彼らは同年代とはすぐに打ち解けます。「SNSですぐにつながり、入社式のときには、十年来の友だちかと思うほど仲良くなっていた」という話も聞きます。その反面、年齢や立場の違う人とコミュニケーションは苦手という傾向があります。tとくに指摘されるのが、自分から挨拶できない人が増えているということです。
家庭では親から、学校では先生から挨拶をしてくれることが理由のひとつとしてあげられます。
「目下の人間が目上の人間を敬って自分から挨拶をする」という習慣が身についていない人が少なくないのです。
少子化時代の学校は、生徒が休みたいと思ったときや、親が休ませたいと思ったら、簡単に休めるような風潮になっています。決して無理をしません。一方、40代や50代の昭和世代は、「よほどのことがない限り、休んではいけない」という常識で育ってきました。
また、少子化で競争がなくなり、高校も大学も高望みしなければ必ずどこかに合格する、いわゆる「全入時代」です。一流大学を目指すごく一部の人を除いて、大学受験で浪人する人も少なくなっています。学力は低下傾向なのに、大学には簡単に入学できるため、挫折経験がありません。さらにほめられて育ってきていることから、「勘違いした自信」をもっている人が多くいます。
彼らは、そうした競争のない温室から、弱肉強食のビジネスの世界にいきなり飛び込むので、仕事がうまくいくことはほとんどありません。今や工場も事務も効率化されてコンピューターやロボットがやるようになりました。新入社員がやれるような簡単な仕事がほとんどなくなりました。いわゆる下積みの仕事がありません。「即戦力」という言葉は聞こえが良いですが、そう簡単ではありません。
ましてや一所懸命、泥臭くがんばるという経験もないため、昭和世代の上司にとって、とても物足りないように感じます。
新入社員にとってビジネス社会が、学校社会と比べて非常にギャップの大きい未知の世界である、ということをしっかり理解しておきましょう。
そうすることで彼らとコミュニケーションを取りやすくなるかもしれません。
出典:
平成生まれの新入社員。その特徴と育て方は?
平成時代の新入社員には褒めるという育成方法?

価値観や考え方が大きく異なっている平成世代に、昭和時代の人材育成のやり方では、平成世代の新入社員は辞めてしまう人が多いでしょう。
そこで、今メディアでも話題の新しい人材育成の方法のひとつとして、『ほめ達』というものがあります。
「ほめる」というアプローチは、職場のコミュニケーションを改善するだけにおさまりません。企業業績に直結する「社員のパフォーマンス」に変化を起こすものとしても注目されています。
「ほめる」とは、自分の心を整え、相手の良さを見出し、自分とかかわるあらゆるものから価値を発見することです。
「ほめる」ことで、企業が待遇やワークライフバランスだけでは社員に与えることのできないもう一つの報酬、「心の報酬」を与えられます。
「心の報酬」とは「成長の実感」と「貢献の実感」を感じること、「ねぎらい」を得ることです。
メンバーの一人ひとりが「成長の実感」と「貢献の実感」、「ねぎらい」を得ることで、能力を最大に発揮できるようになります。
2016年6月22日の日経産業新聞でも「NTTグループが全社にほめ達を導入」という記事が掲載されました。
『ほめ達』は、日本国内だけで年間2万人を超える自殺者が続く異常な事態を打破したい!という思いから設立された協会ですが、この「ほめる」というアプローチを通じてチームメンバーの能力を最大化するチームビルディングのスキルを身につけられることもあり、企業の人材育成研修にも活用されています。
出典:
【PDU対象】「ほめ達!」チームビルディング研修[6PDU付]
人材育成のこれから。ICT化、DX化で取入れるべき戦略とポイント

コロナ世代の「オンライン研修」への移り変わり
企業の人材育成において、人材不足とグローバル競争への対応は兼ねてからの課題となっています。
更に近年では新型コロナウイルスの影響により、育成計画の大幅な変更を余儀なくされた企業も多数ありました。コロナの影響により新人研修が行われなかったことで、「研修」のあり方や意味について考えるきっかけになったという声もあります。現在では、個々の従業員が最大限のパフォーマンスを上げ、企業の業績に貢献していく体制を作るために、企業教育にはICT化とそれによる効率・効果のアップが求められています。
取入れるべき戦略とポイント
1.オンライン研修でのリアクションに気を付ける

研修をする側と、参加者が同じ空間にいないため、相手の雰囲気を把握しづらくなります。進行スピードが速すぎないか、ついてこられない参加者がいないか、積極的に意見を求めるなどして、丁寧に理解度を確認しながら進行するのがポイントです。カメラオフで研修を実施する場合には、チャットによるコメントやリアクションボタンをフルに活用するよう事前説明をするのがよいでしょう。参加者が積極的にコミュニケーションを取りやすいよう配慮するのがポイントです。
2.事前にツールの使い方を学ぶ必要がある
事前に講師側だけでなく受講生側にも事前に操作マニュアルを用意するなど、研修当日に必要な操作が分からないといった事態にならないようにするのがポイントです。Web会議ツールの扱いに慣れていない人がいる可能性も考慮しましょう。当日は補助スタッフを用意して研修中個別に対応できる環境を整えるのも効果的です。
3.時間に区切りを持たせる
オフラインの研修と違い、オンライン研修は参加している受講者の集中力が下がっていないか確認しにくくなる点があります。集中力が下がると研修効果が低下してしまうので、1時間以上に及ぶ研修の場合は、集中力を回復させる休憩時間を計画的に挟むなどすると良いでしょう。研修の中でも、参加者同士に適度な会話をさせるディスカッションの時間を設けることも、リフレッシュとなり、集中力低下を防げるのです。
4.eラーニングの活用

オンラインを用いた研修方法として、e-ラーニングもあります。
eラーニングはパソコンやモバイル端末を使用して、インターネット上で学習ができる人材育成方法です。
e-ラーニングとオンライン研修は、同じ研修のように感じますが、少し仕組みが異なります。
オンライン研修はリアルタイムで動画が配信されますが、e-ラーニングは、録画された動画の視聴がメインとなります。
eラーニング自体はもはや珍しいものではありませんが、最近ではDXの技術を取り入れ自律的な学習を促す「LXP」*1(Learning Experience Platform)の考え方や、昇格テストなどの社内で行われるテストをオンライン化する動きなどがみられます。
たとえば、オンラインツールを組織内に導入し、社員が好きな場所やタイミングで学習を行えます。社内に限らず離れた場所でも学習できるため、好きな時間や好きな場所で、自分のペースで学習を進めることも可能です。メリットが多い一方で、ツールなどを導入する手間や費用がかかったり、必要に応じて教材費用などが発生したりする可能性があるのがデメリットといえるでしょう。
[*1] Learning Experience Platform
https://www.valamis.com/hub/learning-experience-platform
◆人材育成会社にアウトソーシングするときのポイント
企業内の人材育成のため、多くの企業が様々なリソースを活用した人材育成施策を導入しています。しかし、多くの企業が試行錯誤を繰り返しながら、人件費問題や研修内容の専門性といった課題を抱えているのが実情です。
一方、外部の人材育成会社に依頼することで、さまざまなメリットを享受できる可能性があります。ここでは、外部の人材育成会社に依頼することのメリットをご紹介します。
1.専門的なスキルを身につけられる人材育成会社を選ぶ

外部研修では、その道のプロや専門家による講義を受けることができ、社内では学べない、より専門的なスキルを身につけられます。社員は、現場で使われているさまざまなツールやプロセス、ソフトウェアの使い方を専門家から学べます。
また、独自の問題や状況について話し合い、実践的に解決する方法を学ぶワークショップに参加できます。今まで知らなかった知識を吸収するだけでなく、視野を広げることで、新たな発想につながる良い機会です。
2.会社のコスト削減に期待できるのも一つのポイントです。

専門的な研修業務や社員教育のために、専門講師を正社員として雇用するよりも、外部の人材育成会社に委託することでコストを抑えられます。前記のオンラインにより気軽でかつリーズナブルな受講ができます。
そのため、オフィススペースや研修室、設備初期費用の投資や維持などの高価なリソース、その他の経費が不要になります。
また、正社員の福利厚生や休暇を用意する必要がないです。これは、予算が限られている企業にとってはメリットとなります。
さらに、厚生労働省の企業人材育成助成金と併用することで、より経費削減につながります。ぜひ活用してください。
参考:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
まとめ

今の時代は、労働人口の減少や高齢化、雇用形態の多様化している環境です。
社員への接し方(特にほめ方)、DX社会の変化、グローバルなビジネス環境など、外部環境におけるあらゆる新しい課題を抱えています。
コストを抑えながらかつ効率的な人材育成の必要性はかつてないほどに高まっています。
実際、厚生労働省が実施した「労働経済の分析」調査では、半数以上の企業が、競争力を高めるために改善・強化すべきこととして、能力や資質などの人材育成を挙げています。
そこで、企業が競争力を高めるために、どのように人材を育成し、定着させればよいかを考えてみました。
外部の人材育成会社に依頼することは、人事業務の改善を目指す企業にとって多くのメリットがあることは明らかです。
社員が専門家から専門的なスキルを得られたり、社内研修にかかるコストを削減できたりと、人材育成のアウトソーシングは素晴らしいソリューションとなり得ます。
人材育成戦略の改善をお考えの方は、ぜひソフィアコミュニケーションズへの依頼をご検討ください。